![]() 日 記 帳
日 記 帳![]()
観測日記、その他天体のことや身の回りのことなど、思いつくままに書いてみました。 ![]()
02.10.31
星図
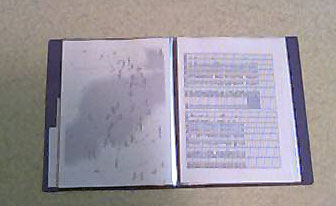
自作の星図です。夜に外に持ち出すには少しでも軽いほうがいいと思いまして、A4をすべてB5サイズに編集し
直してファイルしました。20枚の透明ファイルにステラナビゲータで自作した星図を白黒反転出力したのを右側に
データを左側にファイルしました。
これに日本で見える全ての星座と約1150個の重星のデータが入りました。大きさはB5Sサイズ、重さは280gです。
標準星図2000が重さ1.3kgですのでずいぶんと小さく軽くなりました。ただしデータは重星だけですので別に
星雲星団ウォッチングも一緒に必要ですが。
星見は極力軽装を心がけていますので、そのために試行錯誤するのは楽しいものです。
02.10.27
カシオペア
昨夜は7時過ぎから1時間ほど重星を見ました。最近は日没が早くなり、すぐに暗くなるので7時を過ぎると
星の観測が出来ます。またこれから冬にかけては街の灯りがおちる11頃まで待たなくても、透明度がいいので
早い時間からたくさんの星が輝きます。ただしいつも言っているとおり大気の安定する日は少なくなりますが。
カシオペアの重星を5個スケッチした中で今回のお薦めは6Casでしょうか。角距離が1.6秒角しかなく今の
季節で分離するのは難しいでしょう。当日は気流が荒れていて最初は全然分離しませんでしたが、またに気流が
おさまったときに、ふわっという感じでリングの一部にこぶができたように伴星が見えてきました。
おもわず、「あっ見えた」とつぶやいてしまいました。
カシオペア付近を流すときに大気が安定していたら狙ってみて下さい。
02.10.25
くじら
明るい星はない上に月夜で、肉眼で見える星はほとんどありませんでしたが、双眼鏡のおかげで3〜4個
ほど重星を見ることが出来ました。今夜は雨模様ですので昨夜無理して見ておいて良かったです。
スケッチしたくじらの重星はS390、37、χの3個で、いずれもパッとしませんが37番星は伴星が灰色にみえて
面白いです。
満月の日より星が見えませんでしたので、透明度が良くなかったのでしょう。星をいっぱい見るのには空の暗さ
と同じくらい透明度が影響するものです。ただし星がいっぱい見える日に限って望遠鏡で重星や惑星がよく見え
ないものです。星がキラキラしていっぱい見えるときは双眼鏡で、少々透明度が悪くても空気がじっとしているときは
望遠鏡で重星や惑星が良く見えます。
よく見えないと言う前に、同じ晴れた日でも星空の状態で見る対象を変えてみれば、せっかくお外に出た無駄も
なくなるのではないでしょうか。
02.10.21
満月
帰宅が遅くて双眼鏡も持ち出せなくて、肉眼だけでしばらくお空を眺めていました。
今日の満月はとてもまぶしく輝いていましたが、3等星までは見えていたので星座の形が分かりました。
今朝までの雨で浮遊物を流し去り透明度良くなったのでしょう。満月なのに星座が見えるという少し神秘的な
感じがしました。
夏の星座、はくちょうが北西の空に傾いた頃、東の空にオリオンの左半身がよっこらしょと起きあがって来ました。
夏の代表格さそりには姿を見せられないオリオンは、はくちょうには気を許しているんでしょうね。
さそりを避けるように上がってくるところをみると、よほど毒針が怖いんでしょうか。
02.10.19
私の恥ずかしい絵
をお見せします。なんて似たようなフレーズをたまにみかけますが、HPに掲載するのを躊躇していたスケッチ
をいくつか掲載しました。
いずれも眼視のイメージに近いように描いているつもりですが、とくに木星は難しいです。来年の火星大接近
を前に練習をと思っているのですが、そのころはデジカメを買うつもりですのでどうなることやら。
惑星はFS102ではよく見えますが解像度不足ですし、バイザックでは像が安定しないし惑星用に20〜30cm
の純ニュートンかマクニュートンが一台欲しいです。だって来年の大接近を逃したら次回は目が見えなく
なっているかも知れないし・・。
昔からアポ屈折とF8の純ニュートンはあこがれの的でした。
金もないのに次から次へと欲しい物ばかり。年末ジャンボ宝くじかおーっと。
02.10.17
ペルセウス
昨夜は、月夜でしたがペルセウスの重星を7個ほどスケッチしました。この辺は月がなければ散開星団が
たくさんあって楽しい場所ですが、明るいときは重星が結構まとまっていて楽しめます。前回を含めて15個
をスケッチしました。星見の後半雲が出てきたので少々あわてましたが、1時間ほどの間に10個ほどの重星
を見ることが出来て良かったです。
最近は寒くなって半袖では出れなくなりましたが、蚊もいて蚊取り線香を焚きながらと、夏と冬の狭間のような
気候でした。
今回のお薦めはΣ382Perです。あまりぱっとしない重星ですが、主星の回折リングが非常にきれいで印象的
でした。望遠鏡の機種によっては回折リングが見えにくい場合もありますし、回折リングが伴星の確認を邪魔
する場合もありますが、私はこのリングが大好きです。
02.10.14
おひつじ
昨夜は10月にしては大気が非常に安定して回折リングが微動だにしない素晴らしい状態でした。
おひつじ座の重星6個、内連星1個をスケッチしましたが、ラジアン4mmを使って狭いどころを楽しむ
ことがでしました。望遠鏡がよく見えないの半分は大気の状態ですので、こまめに大気の状態を
チェックして、さっと望遠鏡を出せる状態にしていることが、きれいな星を眺めることが出来る条件だと
思います。
重星とは他に、二重星団やカシオペアの散開星団をいくつか見ましたが北側は少し明るいので、もう一歩
でした。明るさのせいか二重星団は×20(LX40mm)より×33(LV25mm)のほうが微恒星もみえて迫力が
ありました。やっぱり自宅用に20〜25mmの広角アイピースが1本欲しいです。
M42(オリオン大星雲)は10cmでも迫力がありますし、どの倍率で見ても楽しめる対象です。例えば×137
(LV6mm)と×205 (Radian4mm)を比較して倍率が大きくなっても星雲は淡くならず、かえってトラベジューム
の輝きが増して背景と星雲のコントラストが上がったように感じました。
これが倍率の効果かアイピースの性能の良さかはよく分かりません。
最後に惑星本体が輪から落っこちそうな立体感のある土星をみて、終わりにしました。
02.10.10
みずかめ
久しぶりにみずかめの重星を見ました。この星座は形を確認するのは難しいですがαのフォーマルハルト
が力強く輝いていますので、これを基準星にして双眼鏡で探っていけば暗い重星も楽に導入できます。
4個ほどスケッチしましたがω2と96番星は伴星が10等台と暗く確認できませんでした。次回、もう少し
暗い空かバイザックで挑戦してみるつもりです。
手動導入には双眼鏡が必須で、筒を向ける前に必ず双眼鏡で当たりを付けますが、これがまた楽しいです。
そこに星雲星団や天の川がなくても、いろんな星の形や輝きを楽しめます。
ところで、有名な重星は初心者でもその色の違いはすぐ分かりますが、普通は点光源の色の識別はなかなか
難しいです。
107Aqrをずっと見ていたときのことですが、白のペアに見えたり、伴星が暖色系に見えたりしましたが、結局
青白と青に見えたということで、そのようにスケッチしました。スペクトルでその星の色は分かっていますが
自分はそんなことは意識せずに見えたとおりにスケッチしていますので、写真などとは反対の色表現をして
いるかもしれません。みなさんが見たらまた別の色に見えるでしょう。
それはそれでいいと思います。楽しむための星観望ですから。
02.10.07
竜の卵
と宇宙消失が届きました。Amazonに頼んだ2冊のSF小説です。竜の卵は中性子星に生物が・・・。
宇宙消失は人類を震撼させる量子論的真実が・・・。というしろものです。
私は小さい頃からSF小説が好きで数え切れないほど読んでいますが、ドンパチやる宇宙物より
こういうたぐいの小説が好きでした。2冊頼んだのは1500円以上は送料がただだからです。
外は雨です。天文ガイドも買ってきたし、さてどれから見ようかな。
02.10.06
さんかく、おひつじ
一旦は断念したんですが、帰宅して0時頃外を見るときれいに晴れたいたので、稲刈りで疲れて
いましたが少しだけと、望遠鏡を設置しました。
三脚、架台はベランダの自作物置に置いていますので部家の筒とも設置するのに5分ぐらいで終わります。
即、観測に入りましたので外気に慣れていないせいか、大気が不安定なせいか、星があちこち飛び跳ねたり
にじんだりしました。それでも比較的狭い重星を観測できたのは10cm屈折のおかげです。これが20cmの
バイザックだったら跳ねたりにじんだりする星を、特有の肥大化した星像と相まって、接近した重星観測は
不可能だったでしょう。
さんかくとおひつじの重星を見るのは初めてでしたが、この辺は近くにペルセウス、すばるなどがあり
双眼鏡で流して見るとわりとにぎやかで楽しめます。
さんかくのお薦めはιTriでしょうか。光度、離隔とも重星の見本という感じです。15Triは低倍率で楽しめる
貴重な存在です。30倍以下がいいでしょうか、色の対比と5個の星の配列を楽しめます。
時間も遅いし疲れていたのでおひつじの連星Σ305を1個スケッチして切り上げました。
02.10.05
バイザック
朝から稲刈りでもうくたくたです。刈るのは機械がやるんですが、稲を自然乾燥するために掛け乾し
するのが重労働でした。しかし乾燥機で強制的に乾燥した米とは段違いにおいしい米が出来ます。
久しぶりに実家に置いてあるバイザックで星を見るつもりでしたが、薄曇りで断念しました。
重星はFS102に任せてバイザックを星雲星団用にしてますが、赤道儀では機動性がもう一歩なので
いい経緯台を探しています。自作の経緯台もありますが、がたが多くて。
HF経緯台を上手く使えないか今考えているところです。
02.10.01
うお
夕べと今夜は月あかりのじゃまもなくなりましたので、久しぶりに重星を見ました。
うおの重星は今回が初めてで、あまり明るい星はありませんが、ペガススとアンドロメダに寄り添って
いるので導入は難しくありませんでした。
秋の気配か、たまに星が揺れることがあり夏みたいに星がじっとしていないので、離隔の小さいのは
分離が難しくなってきます。
今回のお薦めはうおの65番星です。白のペアで色がないですが、等光で距離や明るさが絶妙で
見応えがあります。また35番星の伴星が灰色に見えましたが、みなさんも伴星の色を観察してみて
下さい。白に見えるか青に見えるか灰色に見えるか。
重星を見るときのアイピースは高くて広角のものがよく見えるのではなく、その重星の離隔と光度に
合った倍率のアーピースがよく見えるアイピースです。ですから自分の観察した経験からの意見と
しては重星観察に限って言えば、4万円のアイピースを2個買うより1万円のアイピースを8個そろえた方が
いいような気がします。
通常は月も惑星も楽しまれるでしょうから、それぞれの観測スタイルにあったものをそろえればいいでしょう。
自分も星雲星団をみる低倍率用は断然広角アイピースが良いです。
02.09.23
中秋の名月
少し満月を過ぎましたが、双眼鏡を三脚にセットして中秋の名月を楽しみました。れいによって雲が
時より流れて大変幻想的でした。
ついでに空が明るかったですが、FS102を出して重星を見ました。はくちょうのアルビレオはいつ見ても
色の対比が爽やかな重星です。その後同じく、はくちょうのs、h314、27番星、Σ2624を導入しましたが
スケッチしたのはΣ2624だけでした。あとの二つはデータと見ためが合わずHPにはアップしませんで
した。
重星ばかりはつまらないのでM57を見ようと筒を向けると、月明かりがありましたが簡単に見つけること
が出来ました。惑星状星雲は空の明るさに強いのかなあ。それと惑星状星雲はOⅢフィルターが効果が
あるようですが、素人が見ても分かるくらい改善されれば一つ欲しいです。
02.09.18
双眼鏡で
11時をすぎたあたりから雲がとれてきて望遠鏡を出すには夜も遅いので、双眼鏡を三脚に固定して
すばる、ヒヤデス、ペルセウスαのMel.20付近を見ました。
月が西に明るく輝いていましたが透明度がよかったせいか、自宅庭先でも星々の集まりを十分楽しむことが
出来ました。
軽く流す程度なら手持ちでもいいですが、じっくり楽しむのなら7〜8倍の双眼鏡でも必ず三脚に固定して眺めて
みて下さい。同じ対象でも別の世界が見えてきて感動します。
02.09.14
明け方の星座
朝3時に目が覚めて空を見上げると、いい天気だったので思わず望遠鏡を設置してしまいました。
東にはもうオリオンが昇っており久しぶりの対面に懐かしさを感じました。
早速、M42のトラベジュームを導入すると鳥の羽ばたきの中心に4個の星が輝き素晴らしい眺めでした。
βOriを見た後、これも久しぶりの土星を導入してみました。気流が安定しておりFS102にラジアン4mmで
カミソリの刃のような輪に黒のサインペンで引いたようなカッシニがくっきりと見えて、A環とC環の濃淡の
違いもはっきりと分かりました。土星本体の影が輪をナイフで切り取ったように写っており本体の帯が茶色
がかっていることも確認できました。
10cmはしょせん10cmの分解能しかありませんが、本体、輪とも大理石を磨いたようにツルツルしたCG
のように見えるアポ屈折が大好きです。
その内に木星も上がって来ましたが、東の空にだいぶ低かったので見え味はもう一歩でした。
次に2インチ天頂ミラーにXL40mmをつけてすばると二重星団を眺めましたが、両方とも余裕で視界内に
入りました。しかし北の空が明るいので二重星団は星が少ないでした。次回は暗い空の実家で秋の散開
星団を楽しみたいと思っています。
重星はOriを2個、Aurを2個スケッチしました。今回のお薦めはθAurです。βOriに似た不等光重星ですが
これよりは確認しやすいでしょう。似たものどうしなので両者を比較して眺めると面白でしょう。
02.09.08
ケフェウス
前回とはかわってケフェウスの重星を導入するのに4個ともすぐに導入できました。
いずれも5角形の中だったのと4個とも近くにあったからでしょう。
今回はοΣ457、1.4秒角がお薦めです。主星の回折リング上に微かに確認できました。
少し光度差もありますが、みなさんも分離できるか挑戦してみて下さい。
02.09.06
秋の気配
昨夜、9時頃帰宅して疲れ気味でしたが、久しぶりに晴れていたので思わず望遠鏡を出してしまい
ました。透明度がもう一歩で僅かに雲も出ていたので、導入に苦労しました。
近くに明るい星か、特徴的な星の配列がない場合はなおさらです。
まず星図で目標付近の配列を暗記して、双眼鏡でそれを確認します。次にファインダーで導入しますが
左右上下逆さまなので、頭でそれに合うように星図のイメージを変えなければなりません。
アストロの正立ファインダーから純正のファインダーに換えて間もないので、導入に少し戸惑います。
また天頂付近になると首が痛くてしようがありません。こんな時は自動導入が欲しくなります。
熱帯夜は導入するのに汗だくだくになり接眼レンズが曇って見えなくなりますが、昨夜は少し風も
あったせいか涼しくて汗もかきませんでした。
朝夕はそこに秋の気配を感じます。
02.09.01
わし座
台風一過後もパッとしない天気でしたが、家族でバーベキューをする事になって夕方、一応望遠鏡を
だしていたら、スカッと晴れてきたので早速わし付近の重星を見ました。
スケッチの間にアルビレオを子供たちに見せました。この重星は夏の代表格だけあって、子供たちも
色が星に付いていると言って喜んでくれました。青とか水色とか言って伴星のブルーに感激したようです。
今回の一押しはOΣΣ178です。離隔は大きいですが、黄色と青のコントラストが素晴らしい重星です。
離隔が狭かったらアルビレオに負けなかったかも知れません。
わしに望遠鏡を向けたときは是非挑戦して下さい。